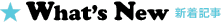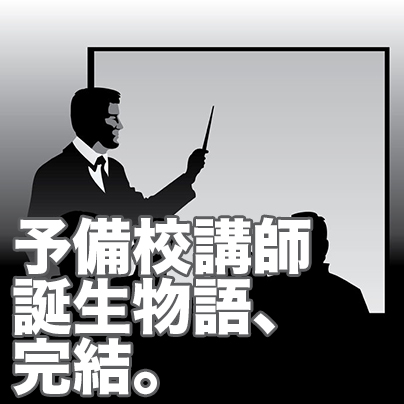
自分自身の学校での体験、
教育実習での教頭先生との軋轢、
不熱心な教師との遭遇などを通じて、
20代の私は「公教育に向かない」という判断をしました。
おそらく、公教育では「おかしいこと」を
「おかしい」とも言えないだろう、
教育改革に取り組んでも制止されるだろう、
懸命にやってもやる気のない教師達の中で
浮いてしまうだろうと考えたのです。
そして私は予備校という選択をしました。
当時の教育産業は今以上に
「教育を商売にするなどけしからん」
という批判的な目にさらされてはいましたが、
学生運動を経験した講師などが体制批判なども含めて
自由に発言しているように見えました。
私は「学校が求めるアンケート評価などを出しさえすれば、
むしろ予備校講師の方が言いたいことを言えるのではないか」
と考え、
「より良い教育をめざす営み」の可能性は公教育よりも
むしろ教育産業の方にあるのでは無いかと考えたのです。
市場経済における競争原理が
改革のエネルギーになると考えたのでしょう。
勿論、その後の予備校職員・講師としての人生を通じて
「競争原理」も万能では無いことや、
現実の社会はそう簡単では無いことを痛感し、
20代の判断が正しかったかどうか、今でもわかりません。
しかし、当時としてはそれが精一杯の判断でした。
私は、以上のような経緯を経て、
大学でお世話になった教授の
「かえって君のような人間こそ、公教育に行って欲しいんだが・・・」
という言葉や、聾学校の指導教諭の
「聴覚障害という重荷を背負わされた子ども達に対する
深い愛情に感銘しました」
というコメントなどを心に抱きながら、
本当は公教育の中でやりたかった
「より良い教育をめざす営み」
を教育産業の中で行うことになったのです。
予備校の住人でありながら、教育について熱く語ると
「どうして学校の先生にならなかったのですか?」
とよく聞かれますが(笑)、
そのような質問への回答としての長い長いお話でした。
お付き合い下さり、ありがとうございました。

|
カテゴリーや各種特集ページからお越しの方は、ブラウザの「戻る」ボタンでお戻りください。